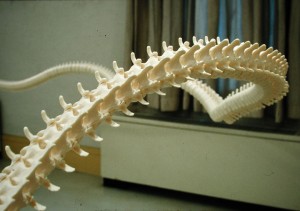頭のおかしい人へ
2011年 10月 19日
ある町の依頼で公園に公共設置の作品を設置した。14、5年前のこと。僕以外の出品作家はアトリエで制作した彫刻を台座に据え付けるものだった。僕は周囲の不安の声をはねのけて現場制作に踏み切った。石材を地面に敷き込んで人一人がすっぽりと入る凹みを大地に穿つ作品だ。
ひと月現場に通い続け、地面に穴を掘りコンクリートを流し込み、石を叩き込む。周辺の住民の目線から感じるに、ある日唐突に現れた「頭のおかしい人」が自分を埋める穴をひたすら掘っている、そんなふうに目に映っていただろう。兄が病死して二日程しか経っていなかった着工当時は鬼気迫る勢いで作業に没頭する他なかった。
現場で作業をしていると、道ゆく人々の冷たい視線を感じることもしばしば。そのうち「俺はここにこんなものを作ってくれと頼んだ覚えはない」とか、税金の無駄遣いだ」などと私に罵声を浴びせる人が出てきた。僕はどんな話もまず耳を傾けたが、制作を止めることなく、毎日現場に通い続けた。
話しかける人も稀にいたが、遠巻きに見ている人がほとんどだった。毎日買い物袋を提げて行き過ぎる初老の女性も行き過ぎるだけの通行人の一人だったが、制作も佳境に差し掛かったその日は何かが違っていた。
その女性が初めて私が制作している現場で足をとめたのだ。そして、おずおずと私に差し出したのは、一本の缶コーヒーだった。その方は「初めて缶コーヒー買ったの」とおっしゃる。距離をとっていた人が実は一番近くで見守ってくれていたのだ。あーあの時の缶コーヒーの温くて甘かったこと!
時は下り、やさしい美術プロジェクトを設立して5年が経ち僕は作品搬入のため新潟県立十日町病院にいた。窓ガラスに作品を設置していると、背後から話しかけられる。振り返るとそこにはパジャマ姿の入院中であろう女性がぽつりと立っていた。差し出された手には缶コーヒーが!いうまでもなく、その缶コーヒーはあの時と同じ味がした。