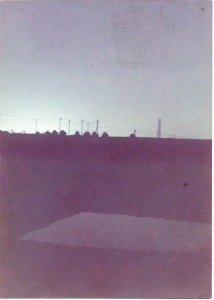<1月2日付けブログの続編>
大島の入所者が語る「故郷(ふるさと)」とはその背景にある過ぎし日々の途方もない長さ、人と人を隔てる受け止め難い障壁の重さ、どれをとっても私が体験してきたどの物差しにも適うものではない。かといってそれをさも理解したかのように「次元がちがう」と別棚に据えるのは大事な何かを放棄する気がしてならない。確かに私はハンセン病の回復者の方々と親密に接する機会を得て、その心情にふれる場に身を置くことができた。しかし、それはほんの3年間であり、大島青松園101年の歴史の末尾。人類にハンセン病が現れた時代は定かではないが、数えきれない年月のほんの一瞬に立ち会っただけである。
私には明らかに何かが欠けている。先述のように私は典型的な現代の日本に生を受けた。私自身を構成する「風景」に不動不変の心情は生まれない。それこそその「風景」が何万年、何千万年を費やして育んだ存在の根拠ごと削り取っていく様をただ目の当たりにしてきた。そこには薄い皮膜のような地表に存在する生きとし生けるものの営みへの尊厳は認められない。私はそれをさして痛みも感じず傍らでぼんやりと眺めてきた。風景との関わりは人との関わりに通ずる。血と肉を分け合うような濃密な「関わり」は物心ついた頃には私の周囲にはなかった。あるいはすでに方々分断され、つながりのなかにある自分を感じることができなかった。自分がまるで密閉された容器のように素っ気なく感じた。
「入所者と私が似ている」というのはいかにもおこがましい。しかし、入所者と接するなかで多くのエピソードにふれ、見聞きしたことを古い地図に投影しながら、次第に鮮明になっていく光景に息をのみ、心がふるふるとうち震え、涙がしとどにあふれた。そのとき私の細胞が 共鳴しているのを確かに感じた。
この感覚は大島にはじまったことではなかった。病院での取り組みの様々な局面に出会い、痛み、苦しみもだえ、憂い、迷い、悩み、突き抜け、よろこび、はればれとし、多くの感覚を抱きしめた。その度に「この感覚が最初で最後かもしれない」と思った。幸いそれは何度も私に訪れた。
取り組みの目的がそこにあるのではないが、私は私自身のために不可視のつながりの糸を恢復してきたのだと思う。 その歩みの先に「大島」があった。
ある入所者がこうおっしゃった。
「私は大島に入所して60年になる。らい予防法が廃止になって入所者は故郷に帰ることがゆるされるようになった。でもね、50年も60年も経って故郷に帰っても、記憶に残っている風景はそこにはないんだよ。知っている人もいない。ましてや親族もいなければ、実家が建っていた跡すらない。大島に閉じ込められてからというもの、故郷への思いはそれはそれは強いもんだった。でも、帰ることのできる故郷はどこにもなかった。故郷はね、心の中にそのまま大事にしまっておくことにしたんだよ。」
ある方はわたしにこうつぶやいた。
「私たちは最後の一人になるまで、終の住処として大島で暮らしたい、そう思っているんだよ。」
法律が廃止されたとて、人の凝り固まった偏見の心がいとも簡単に解きほぐされるとは限らない。経てきた時の流れはもとには戻らないのだ。国のつくった制度に翻弄され、見えない感情の軋轢をかいくぐって生き抜いてこられた入所者が発する その言葉の真意は今の私にはつかみきれていない。でも本人たちにしかわからないとか、きっと大変だったんだろう、などとという感情のなびきでは済まされない、きりきりとした心の軋みを私はずっと感じ続けている。なぜだろう、何なんだろう、この感じは。自分でも焦点が合わないままの感情の焰を携えて私はまた、大島に向かう。
私が芸大を目指し、浪人生だった18歳の夏。先述の山賊峠にブルドーザーが入り、灌木林はすべてこそぎとられた。山賊峠の緩やかなカーブを描いた軌跡は土砂のカオスのうちにかき消され跡形もない。方向性を持たないキャタピラの轍が巨大なドローイングを描いていた。表土ごと剥がされた植物のない大地は、やはり砂漠を思わせた。造成前には見通せなかった風景が褐色の砂漠の向こうに立ち現れる。折り重なる屋根のシルエットが人の営みを感じさせ、それが実際の距離よりもずっと遠くに感じられる。
私は当時の仲間4〜5人をそそのかし、このむき出しになった大地で作品を制作しようと声をかけた。月曜日から土曜日までは土木作業員以外は立ち入り禁止。平日は例のごとくブルドーザーの単調な排気音が轟き、土砂粉塵が渦巻いていた。私たちは土曜日の夕方、作業員が仕事を終え、人がいなくなったのを見計らって額にタオルを巻き、スコップ、つるはし片手に造成地に侵入した。
私たちが実行したのは、大地に方形の池を作り、そこに水を満たす、というミッションだった。 夜中おなかがすくと、造成地のはずれにある私の実家に行き、母が握ったおにぎりをほおばった。全身どろどろだった。夜を徹して作業し、翌日の日曜日を迎える。日中も休みなくひたすら掘り続けた。休めばそのまま動けなくなるような気がした。後日談だが、母の話では「造成地になぞの若者たちが現れ何か良からぬことをしている。」という噂が立っていたという。母は知らないふりをした。近所付き合いのある警察官のお宅は、うすうす私のしていることを知っていたようだが…。今思えばこういう大人に血気盛んな若者は人知れず助けられているのである。
さて、方形の池の掘削作業である。難しいのは水で満たすために水平をとらなければならない。当時の私には水糸をはるなどという知恵も技術もなかった。目測、つまり勘を頼りにとにかく掘り進めるしかなかった。一睡もせず、何から何まで体力任せ。日曜日も日が暮れて夜に突入する。掘る手は思うようにはかどらない、気持ちは萎えてないのだが体がついてこない。翌朝までに本当に完成するだろうか。夜があければ、私たちは造成地から立ち去らなければならない。残ったメンバーは私と近藤歩、鈴木敦の3名。
夜明け前、とうとう完成を迎える。明かりのない場所では空が一番明るく感じられる。それとは対照的に大地は深く黒い闇に近づく。その漆黒の内に10メートル×15メートルほどのしっかりとした辺で切り取られた空が現れた。わずかに明度を持った空が掘った水たまりに映り込んでいる。私たちの二晩を徹した営みは仄かで儚いけれど、その光景は想像していたよりもずっとダイナミックに感じられた。膨大な作業の集積がそこに感じられないのが、またいい。私たちは夜明けの刻々と明るさを増す様子と同調するかのようにただ無心に眺め続けた。
肉体を酷使し大地と関わった充実感で満たされたあのとき。私はほんの一瞬ご褒美をもらったようなあの感覚を、青春の宝物として今も心に抱いている。
まもなく夜は明け、キャタピラの轍が影を落とし、存在感を放ち始める。一時的に満たされた静謐な空気は徐々に日常の彼方に吸い込まれていった。
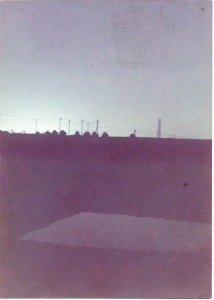
ビデオも撮ったはずだが…数少ない残っているカット